
皆様にとってはどんな一年でしたでしょうか?
本年もまだまだ元通りの日常とはいきませんでしたが、少しずつイベント活動を再開させたりなど、前向きに頑張ってきたダートフリーク。
そしてこんなご時世でも新しい事に挑戦し続けてきました。
その新しい活動の一環として、発足したものの一つに、ダートフリーク家庭科部があります。
今回は、そんな家庭科部の活動、2021年の締めくくり!

お正月になぜ熊手?
熊手は本来、落ち葉などを一度にかき集めるのに便利な農具。
そんな熊手をお正月に飾るのは、その「かき集める」という使い方から、よい運勢、金運、財運など、様々な福を一度にかき集めてくれる。という考え方からだそうです。
また、厄を掃き清める神聖な道具という側面もあったことから、招福と厄除けの縁起物とされてきました。
その熊手に、更に様々な縁起物で飾り付けることで、翌年の福を願う習慣として熊手を飾るようになったようです。

熊手に飾る、縁起物
今回手作り熊手を作るにあたって、熊手に着ける飾り=指物(さしもの)についても調べてみました。
普段何気なく目にしているものや、年末年始によく見かけるなーと思うものには、実はこんな意味や願いが込められていたんです!
おかめ
縁起物でよく見かける、おかめの面。お多福と呼ばれることもあるこのお面は、読んで字のごとく「多くの福を呼ぶ」と言われています。色白く、ふっくらした顔立ちと優しい表情は、昔は福を呼ぶ好ましい顔立ちとされていたのだとか。
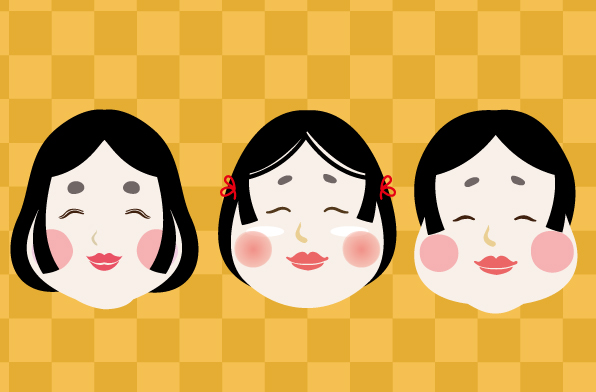
扇子
末広がりの形や、神様に舞を奉納する際に用いられたことから、縁起物として親しまれている扇子。
神様のご利益が宿ると考えられています。
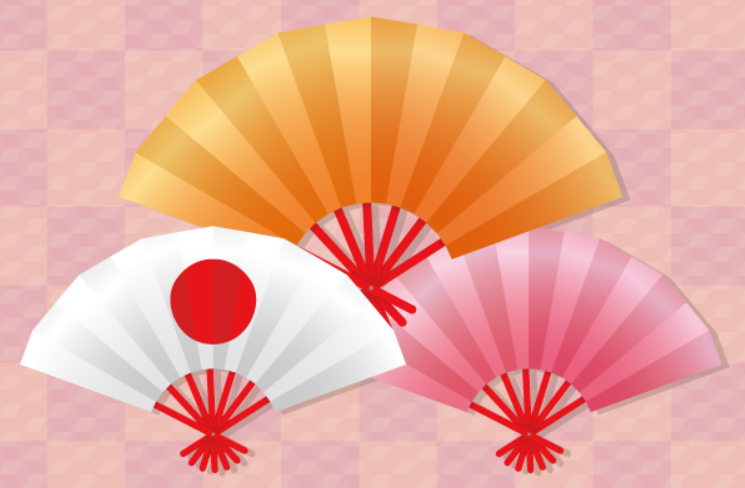
小判
古くは江戸時代から、客商売のお店で、商売繁盛を願って飾られています。

うちでの小槌
振るうと願いが叶う、伝説の小槌。
日本の昔話でも、鬼が宝物としてもっていたり、七福神の一人である大黒天の持ち物であったりと、富の象徴として登場します。

米俵
日本人にとって大切な食べ物。お米。
お米は古くから俵に詰めて保存されており、お米がたっぷり詰まった米俵は、飢えを知らない富の象徴とされてきました。七福神が乗る宝船にも、五穀豊穣の象徴として米俵が積まれています。
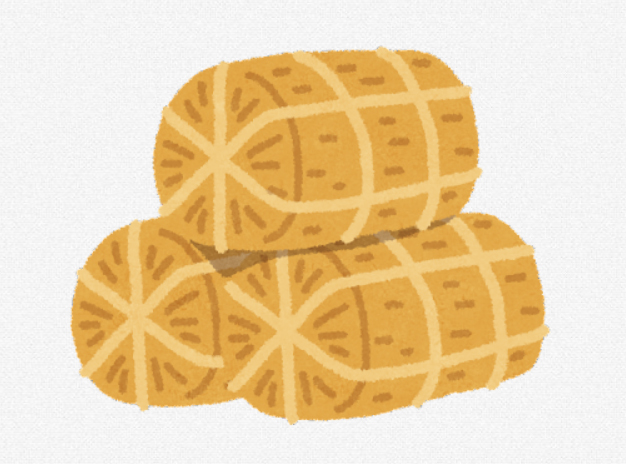
紅白の御幣(こうはくのごへい)
鏡餅に飾られている、あの紅白の紙。あの飾りは御幣(ごへい)と呼ばれ。神様へのお供えものとして使われています。紅白には厄除けの意味があるといわれており、家内安全・商売繁盛の願いが込められています。
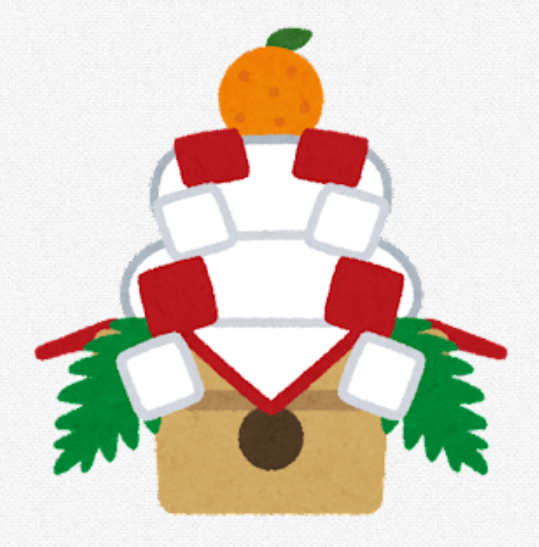
この他にも様々、縁起ものをモリモリに盛って、福を最大限にかき集めたい!という野望を胸に、家庭科部、初めての熊手づくり、早速スタートです!
熊手を作ろう!
毎度のごとく、完成イメージから作ります。
今回は、縁起のよい指物に加え、ダートフリークの特色をふんだんに乗っけた熊手を考えました!

はい!tomoさんお手製、完成予想図がコチラです。
中心にはお多福顔の愛らしいおーにわさん。やんごとなき微笑みを湛えてらっしゃる…。愛おしい…。
「お目出"たい"」にかけて、"タイ"ヤ。
「"繁"盛するよう"努"力す"る"」で"ハンドル"。
など、オリジナルの縁起ものも考えました!
そしてこのデザインを実際に作りたいサイズに印刷した後、厚紙に貼ります。
というのも、今回の熊手製作計画は、まずは厚紙のベースを作り、その上にちりめんを貼ったものを組み立てようというもの。
相変わらず家庭科部全員が未経験の作業ですが、そんな事は気にしません!
思いつくままエンジョイして作っていきます!
というわけで、厚紙に貼った図案がコチラ。


しかし家庭科部はこれでは終わりません。
厚紙に貼った図案に沿って、キレイにハサミでパーツごとに切り分けます。

じゃーん!
キレイに切れました!
大まかにグルーピングしてケースに入れておくと、組み立ての際に間違いにくくなるのでおススメです👍
あとは、設計図と切った厚紙それぞれに…

このように、重ねる順番の番号を振っておくとGOODです!
組み立ての際は、1から順番に下から重ねていくイメージです。
厚紙と設計図の準備ができたら、続いてはお待ちかねのちりめんを貼る作業です!

京都・多加楽(たからく)本舗さんの、手芸用端切れを買ってみました!


高級感のあるよい質感~~~~!
様々な色や柄が入っていて、大量に使う訳ではない場合にはとってもお得感があります!
今回の熊手づくりにはぴったり大当たりのお品でした!

このちりめんを色分けして、使う箇所ごとに付箋のメモを貼り、準備は完了。
次回はこのちりめんを厚紙に貼っていきます!
次回の更新は年越し後の予定です!

皆様よい年末年始をお過ごしくださいませ
